声を鍛えることは大切ですが、声だけが良くなっても効果的なコミュニケーションは実現しません。
前回は【声だけ良くなっても何もならないよ!】というタイトルで歌声、ボーカルにフォーカスをあててお伝えしました。
さて今回は演説、商談、会話や対話などでの「良い声」と「伝わる声」の違いをお伝えします。声だけに頼らないコミュニケーションのポイントを紹介します。美しい声を持っていても伝わらない話し方と、真に伝わる話し声の本質について考えてみましょう。
▼前回の記事

声が大きければ伝わるといったウソ
まず、多くの人は、声が良ければ自ずと伝わると思い込みがちです。例えばナレーター、テレビのアナウンサーやキャスターのように、声が通り心に響く人は確かに魅力的です。しかしその一方で、声だけ良くても伝わらないケースも数多くあるのです。
というのも、聞き手の心に届くのは声だけではありません。言葉の選び方、表情、姿勢、間の取り方など総合的な要素の組み合わせなのです。声は「耳で聞こえる部分」であって、真のコミュニケーション力はその奥に隠されてある要素から成り立っているのです。
通る声を出しているのに聞いてくれない
通る声を出しているのに相手に届かないのには理由があります。
以下の事例から分かるように、「通る声」を体感、手に入れるだけでは不十分です。相手にきちんと理解してもらい、共感を得るためには、次の点を意識する必要があります。
- 内容の整理:アウトプットのために、論理的に整理された内容を簡潔に話す
- 適切な声とパラ言語情報:聞き手に応じた声と調子で話す
- 傾聴と共感:相手の話をきき、共感する姿勢を示す
- 言葉選び:相手が理解しやすい言葉を使いながら話す
今回も事例を交えながら見ていくことにしましょう。(事例の苗字は架空の人物です)
【事例1:会議での発言】
まず、会議での発言の例です。
大越さんは大きな声で自分の意見を主張します。しかし、発言内容は整理されておらず、論理が飛躍しているため、周囲は聞いていても理解できません。その結果、彼の意見は聞き入れられませんでした。これは声の大きさは確保できていても、内容やアウトプットのための整理の方法に問題があったためです。
【事例2:顧客対応】
事例その2は、顧客対応です。
負貝さんは、電話対応で、非常に大きな声で早口で説明します。声が大きすぎるのか、顧客は責められているようで焦燥感を覚えます。落ち着いて話を聞くことができません。その結果不満を抱えてしまいました。 この場合、声のトーンやテンポ(特に緩急)、ポーズ(間)、そして言葉選びに問題があったのです。
【事例3:プレゼンテーション】
事例その3は、プレゼンの場面です。
営業部の薄井さんは声の音色が明るく発音も明瞭です。しかしプレゼンテーションでは
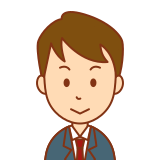
話は上手いが内容が薄く感じるからあまり信じられない。
と評価されてしまいます。それは聞き手の課題や顧客のニーズを理解せず、一方的に自社製品の説明ばかりしているからクレームが多く入っているからです。
声の良さより、相手の状況を理解した上での内容の適切さと伝え方が重要だったのです。
【事例4:電話対応】
事例4は電話での対応です。
カスタマーサポートの真平さんは、滑舌トレーニングで明瞭な声を身につけました。しかし顧客からは
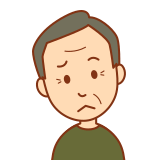
機械的で冷たい。
というクレームを受けています。最近ではAIを使った自動音声で対応している企業もありますが、真平さんよりもまだAIの方が温かみがある気がします。これなら自動音声の方が良かったのかもしれません。
声は明瞭でも形式的なマニュアル対応ではなく、相手の感情に寄り添う言葉選びや共感を示すトーンの届け方が大切だったのです。
【事例5:友人との飲み会】
最後の事例は友人とのやりとりです。
声の大きな折我さんは、友人と飲んでいる時、酔った勢いで一方的に喋りまくってきます。聞き手の反応を無視し、自分の話ばかりを続けるのです。つまり、相手の話の内容を遮って自分の話しにすり替えてしまうことをやっているのです。言うなれば、コミュニケーションにおける「共感」「傾聴」を勘違いしていたためです。音声を「きく」ことに敏感ゆえの「きき間違いや解釈の違い」なども出てきます。また「自分にとって都合の良いきき方」をしている場合もあります。
そんな折我さん、一度友人からの忠告を受けて気をつけるようにしてみたものの、気づいたら元に戻っています。これでは友人も嫌気がさし一緒に飲みに行ってくれなくなりました。
まとめ:声力®=(声の良さ+パラ言語情報)×声を磨く練習
さぁ、いかがだったでしょうか?
声だけ良くなっても、内容までが相手に自動的に伝わるわけではありません。コミュニケーションには「伝える内容」「表現力」「伝わる工夫」が不可欠です。自身の声の魅力とともにその使い方や伝え方も磨くことが、より良い人間関係やビジネスシーンにも繋がります。ここまでやって本当の声力®となるのです。声、感情、表情を探求するとともに、「伝わる」ための工夫も忘れずに取り組みましょう。



