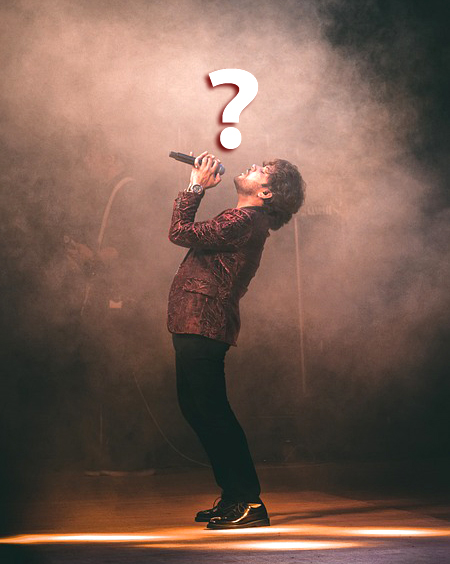現在では、
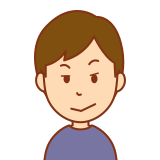
声だけ良くなれば何とかなる。
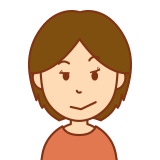
声が良いと良い印象を与えられる。
このように思われがちですが、それは大きな誤解です。
確かに美しい声は魅力的です。しかし声が良いだけでは相手にメッセージが伝わるわけではありません。本当に大切なのは、「伝える力」「伝わる力」と「聞き手に響くかどうか」です。声の良さはあくまで土台であり、その上にしっかりとした伝え方や魅力を加えることが必要なのです。
声が良い=伝わるのウソ
今回は、歌、ボーカルにフォーカスをあてて語っていきましょう。
さて、多くの人は、声が良ければ自ずと伝わる歌だと思い込みがちです。ただし、声の良さだけで歌う歌が感動するとは限りません。声の要素はあくまでお城の石垣のような土台です。
音域は広いのに歌うと上手く聞こえない
つまり、声の広がりや高音が出せることだけが上手な歌唱に繋がるわけではないのです。音域が広くても以下の点が欠けていると、感動する歌声とは評価されません。
そこで事例を交えながら一緒に見ていくことにしましょう。(事例の苗字は架空の人物です)
【事例1:カラオケの経験】
カラオケ好きの欠田さんはJ-Pop好き。高音も低音も出せる広い音域の持ち主です。発声練習も欠かさず、技術的には申し分ありません。しかし友人とのカラオケで
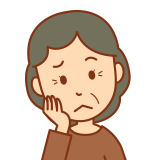
なんだか心に響かない
と言われることが多いのです。
原因を探ると、歌の世界観や感情表現に乏しく技術的に正確に歌うことだけに集中していたことが分かりました。具体的には正確な音程(ピッチ)、正確なリズムなどです。もちろん技術も大切ですが、歌に込められた感情を理解し表現することが欠けていたのです。歌うセンスは誰にでもありますから、そこを探求していなかったのが原因でしょう。
【事例2:バンド活動】
バンドを組んで、あちこちでライブ活動するバンドのボーカル鵜材さん。以前通っていたボイトレスクールで2ヵ月程度で高音域発声法トレーニングを学びました。そこで驚異的な音域を獲得したのです。しかしライブでの評価は今ひとつ・・・。
お客さんからは、
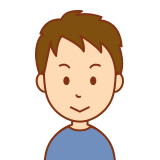
確かに音域は広いいけど、煩いだけ!
という感想が多かったのです。
理由としてはメソッドを短期でマスターしたにも関わらず、リハでいろいろ試していなかったこと。また歌詞の意味を伝える工夫や、観客との一体感を作る表現力が不足していたこと。さらにマイクの使い方が発展途上だったことが理由でした。言い換えると、声の良さより楽曲を通じて何を伝えたいのか?セトリ(ライブでのセットリスト)はどう組み立てるか?といったライブのストーリー性とメッセージ性をイメージしたパフォーマンス力が欠けていたのです。

【事例3:合唱団の経験】
合唱団の出杉さんは、個人練習で声量や音程を徹底的に鍛えました。しかし指揮者からは
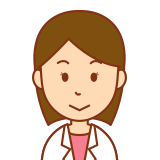
技術は良いし音程は合っているようです。でもハーモニーに溶け込めていませんね。
と指摘されたのです。
他のメンバーとの調和や全体のバランスを考えず、自分の声を前面に出しすぎていたのが理由です。個人の声の良さより、周囲との調和や全体の中での自分の役割理解が不足していたのです。つまりピッチは合っていても、その曲に対しての歌声のチューニングの仕方(♯気味なのか?♭気味なのか?クイ気味の曲か?タメ気味の曲なのか?等々)、相手とのニュアンスの歩み寄りが欠けていたのです。その結果、全体的としてブレンドされない合唱となってしまったのです。
以上、トホホ3つの事例でした。
まとめ:歌も聞き手とのコミュニケーションです
実は声だけでなく、伝えたい内容、相手への配慮、感情表現、そして場の雰囲気を読む力など、歌う時も総合的なコミュニケーション能力を磨くことが、真に「伝わる」ための鍵なのです。声は道具であり、それをどう使いこなすかが本当の課題なのです。
言い換えると、声だけ良くなったところでそれがそのまま聞き手に伝わるわけではありません。自身の声の魅力とともに、その使い方や伝え方も磨くことが、より良い歌唱にもつながります。声の力をつけるという事は、声を磨きつつ使い方や伝え方を養うのです。そして常に「聴いている人に伝わっているかどうかを意識する」こと。これが重要なのです。これらも含めてボイストレーニング、ボーカルトレーニング。そのように考えています。

次回は、話し言葉(プレゼン、やりとり編)をお届けいたしましょう。